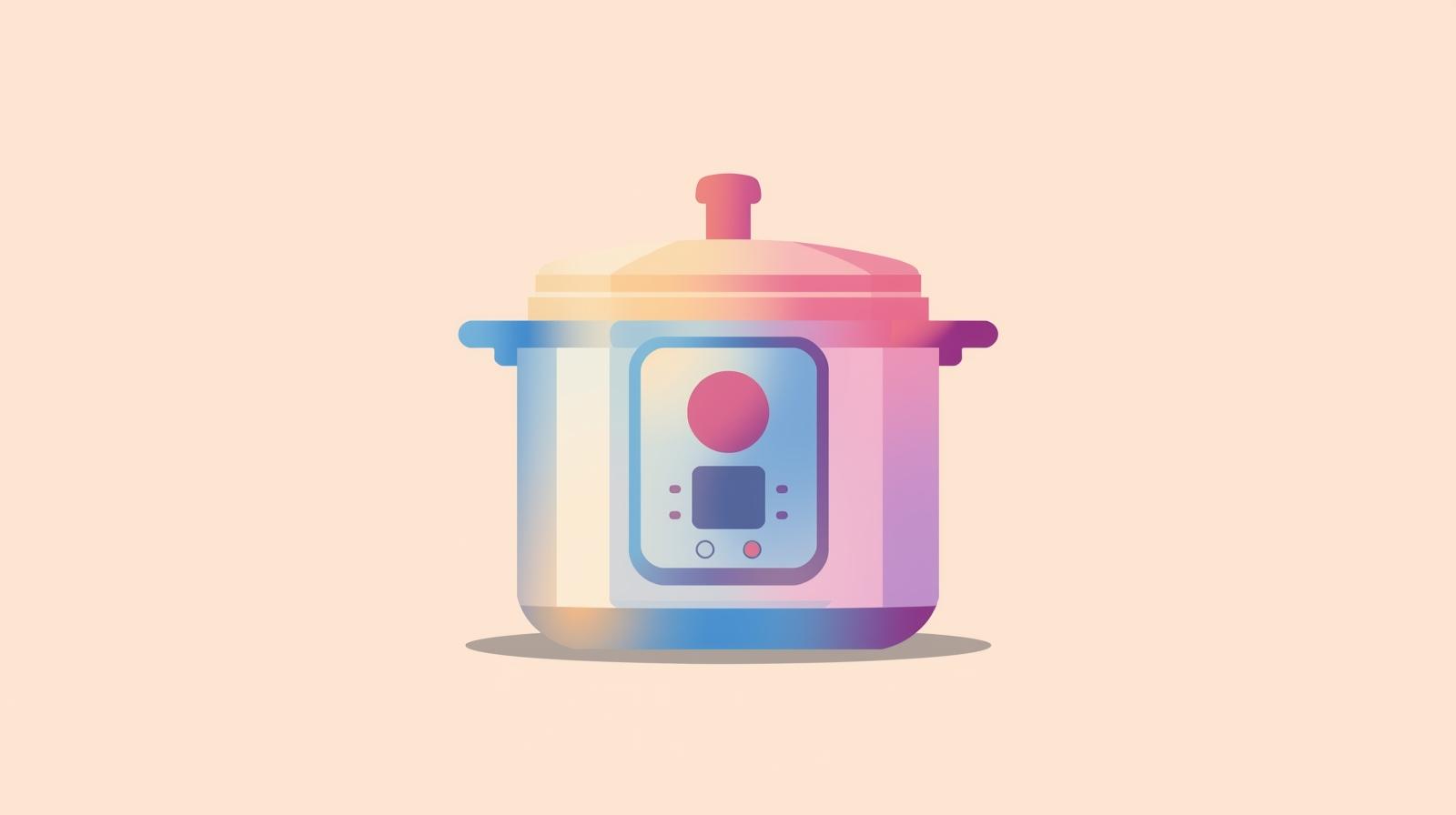🗞 「圧」って、誰が測ったんだろう。
Aぇ! groupの草間リチャード敬太さんの逮捕報道の中で、「国分太一さんから“圧”を受けていた」という記事が出ました。
……“圧”?
それって、数値でも証拠でもなく、人の感じ方のはずです。
でも記事を読むと、「感じていたようだ」「苦悩していたらしい」といった曖昧な表現が並び、読後には“本当に圧があった”ような印象が残る構成になっています。
🔍 「〜ようだ」が積み重なると、事実に見えてくる
この記事で何度も登場する「〜ようだ」「〜と聞く」「〜らしい」。
これは本来、断定を避けるための慎重な表現です。
ところが、何度も重なると読者の中で
“そうらしい”が“そうなんだ”に変わっていく。
SmokeOutは、この手法をレトリック技法「連鎖強調」と呼びます。
根拠の強さは変わらないのに、印象だけが強化される構造です。
UNESCOの『Journalism, “Fake News” & Disinformation』(2018)でもこう警告されています:
“Avoid drawing general conclusions from limited evidence.”
(限られた証拠から過度な一般化をしてはならない)
この記事はまさに、「曖昧さを繰り返して確信に見せる」構成になっているのです。
💬 “圧”という言葉が便利すぎるとき
“圧”という言葉、最近よく見ますよね。
怒鳴られたわけでもないのに、なんとなく感じるプレッシャー。
でも、この記事ではそれを本人の代わりに説明してしまっている。
引用されている場面を見てみましょう。
「リチャード、サボってるでしょ」
「信じられないよ」
番組内ではバラエティの流れで交わされた発言で、番組公式Xでも「#サボり疑惑?」と冗談交じりに投稿されています。
しかし記事では、このシーンを「プレッシャー」「圧」と再解釈。
つまり、笑いの場面を“苦悩の伏線”に変えているんです。
🧠 事実と推測は混ぜない
IFJ(国際ジャーナリスト連盟)の『Global Charter of Ethics for Journalists』(2019)はこう定めています:
“Journalists shall distinguish between fact and conjecture.”
(記者は、事実と推測を区別しなければならない)
この記事では、
「国分さんの発言」=事実
「草間さんがプレッシャーを感じていた」=推測
この2つが同じ段落に並べられています。
その結果、「圧」という言葉だけが“中立っぽい事実”のように残ってしまう。
🎭 “愛情”まで「圧」にしてしまう構成
記事の後半では、国分さんの優しい言葉が紹介されます。
「来たくても来られないファンもいる」
「DASHを見てファンになった人もいる」
普通に読めば励ましの言葉です。
でもその直後、「それを圧と感じていたのかもしれない」と続く。
……え、それも“圧”なの?
この構成は、レトリック技法「対比(Contrast Rhetoric)」を用いて感情を揺さぶる典型例です。
“優しさと苦悩の対立”というドラマを作り、読者の共感を誘う。
けれど、それが事実を超えた演出になっていないか——そこを見抜くことが大切です。
🪶 見出しリライト: “圧”ではなく、人の呼吸で語ろう
元タイトル
草間リチャード敬太が苦悩していた“国分太一からの圧”、『DASH』でスタッフが不安視した“イジり”
新タイトル(SmokeOut基準)
「リチャードはリチャードのままで」——『DASH』で映っていた先輩と後輩の“本当の距離”
見出しから“圧”“苦悩”“不安”といった感情語を抜くだけで、報道は「決めつけ」から「見つめる」へ変わります。
🌻 まとめ:圧を測るより、関係を見よう
“圧”という言葉は、人間関係を一瞬でドラマ化できます。
でも、現場にはもっと多くのやりとりがあって、笑いも、緊張も、敬意もあったはずです。
報道の使命は、「誰が圧をかけたか」を決めることではなく、「何がどう見えたのか」を正確に描くこと。
UNESCOのガイドライン(出典)もこう述べます。
「報道は、人々の恐れや希望を利用するものであってはならない。」
“圧”という言葉が一人歩きするとき、その裏にあった思いや努力まで“見えなくなる”ことがあります。
ニュースを読むときは、「それは誰の言葉?」と一度立ち止まるだけでいい。
それだけで、記事の景色が少し違って見えるはずです。