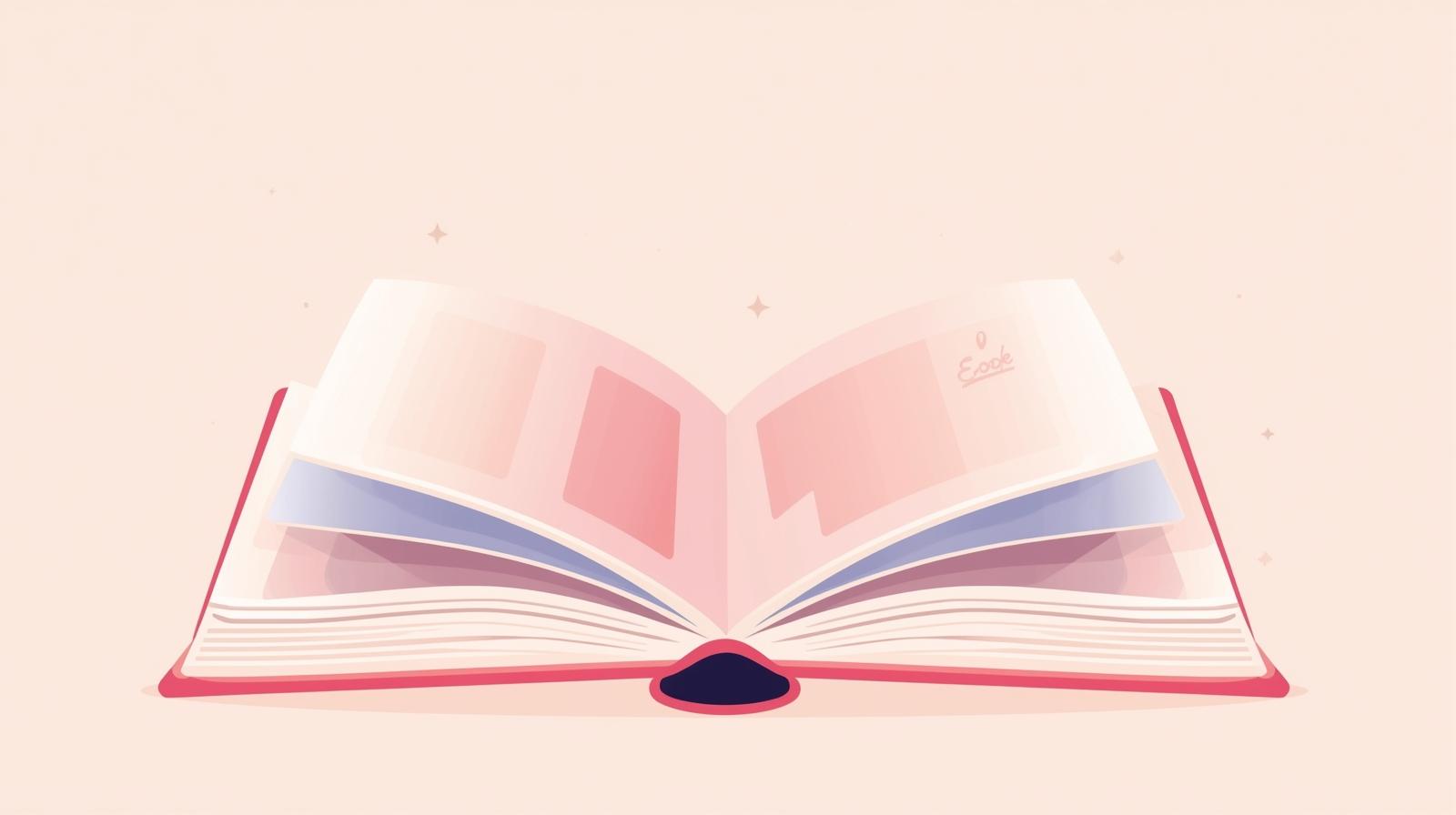「面影がない」って、ニュースになるんだっけ?
髪を伸ばしたら「印象がらり」。
ひげを生やしたら「誰か分からん」。
——その言葉、ちょっと強くないですか?
2025年10月9日、西スポWEB OTTO!の記事が
俳優・小説家の水嶋ヒロさんの“近影”をめぐって話題を集めました。
「面影ここまでないのも」人気絶頂期の結婚から16年…水嶋ヒロ〝印象がらり〟現在の姿に「写真見ても誰か…」「水嶋ヒロさんとは思わなかった」
SNSの投稿を引用しながら、記事タイトルはこう始まります。
「面影ここまでないのも」
「印象がらり」
ネットの声として、
「誰か分からん」「面影ないね」「ここまでないのも珍しい」
とコメントが並びます。
でも——それってニュースじゃなくて、驚きの実況中継じゃないでしょうか。
🔍 構造:感情を共有させる「驚きの三段論法」
この記事の構造を整理すると、こんな流れです。
A:近影が投稿される(事実)
↓
B:「印象がらり」と形容(評価)
↓
C:SNSの驚きコメントを多数掲載(感情共有)
↓
D:「珍しい」「話題」と締める(一般化)
これはSmokeOutでいう「感情三段論法」。
「驚く(B)→共感(C)→正当化(D)」の順に、
読者の感情を“自然に正しい反応”に誘導します。
レトリック的には、
- バンドワゴン効果(みんな驚いてる→私もそう感じる)
- 誇張法(ハイパーボリー)(“ここまでないのも珍しい”で驚きを増幅)
がセットで使われています。
💬 「面影」も「印象」も、主観のかたまり
そもそも「面影がない」とは誰の基準でしょう?
外見が変わることは、歳を重ねた証であり、
変わらないことこそ不自然です。
しかし記事は「珍しい」「驚き」といった語彙を繰り返すことで、
“変わる=話題になる”という構造的前提を作ってしまっています。
こうした報道は、UNESCO報道倫理ガイドライン が指摘する
「個人の外見や身体的特徴をセンセーショナルに扱うことは、尊厳の侵害にあたる」
に抵触するおそれがあります。
つまり、「驚かせること」が目的化した瞬間、報道は“他人の変化”をネタにしてしまうのです。
🧠 もう一つの問題:匿名の「ネットの声」
「誰か分からん」「ここまでないのも珍しい」
これらのコメントはすべて出典不明。何人が発言したのかも示されません。
「引用は出典の明示ができない場合、代表性を誤認させてはならない」
と明記しています。
つまり「ネットの声」という匿名集合は、記者が好きな感情を選び取って“世論”として演出できる装置なのです。
🪄 見出しリライト:驚かせないタイトルで、尊厳を守ろう
元タイトル:
「面影ここまでないのも」人気絶頂期の結婚から16年…水嶋ヒロ〝印象がらり〟現在の姿に「写真見ても誰か…」「水嶋ヒロさんとは思わなかった」
🌤 改善案(SmokeOut基準):
水嶋ヒロさん、近影を公開 現在は投資家としても活躍
驚かせる必要も、「みんなが驚いてる」必要もない。
報道ができるのは、人の変化を事実として静かに伝えることです。
🌻 まとめ:「驚き」はニュースの形をしているけれど
記事が「驚き」を前提に構成されるとき、読者は“感情のテンプレート”を押し付けられます。
「驚くのが正しい」「懐かしいと思うべき」——そんな空気が、報道の中に密かに流れています。
Council of Europe「Resolution 1003」 は、
「報道は感情を利用するのではなく、理解を促すものでなければならない」
と定めています。
外見の変化を驚きで消費するのではなく、生き方の変化を理解する報道へ。
ニュースは、感情の実況ではなく、時間の記録であるはずです。